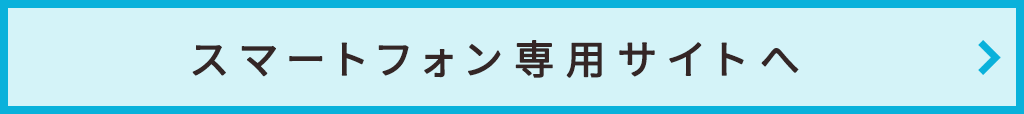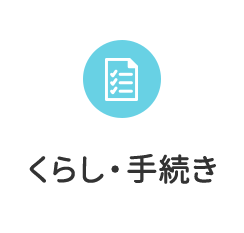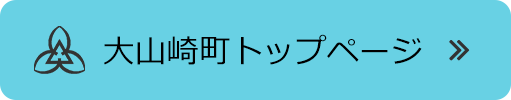後期高齢者医療制度限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和7年7月3日更新)
1か月間の医療費等が高額になりそうなとき
手術・入院等により医療費等が高額になりそうな場合には、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
ただし、申請する世帯で後期高齢者医療保険の保険税の滞納がある場合や、市町村民税を申告していない方がいる場合には限度額証を交付できません。
なお、所得や世帯構成によって限度額は異なります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
後期高齢者医療制度 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)(令和7年7月3日更新)
※限度額適用認定証を提示していても複数の医療機関や複数の方の自己負担額を合算して世帯の限度額を超える場合には、別途高額療養費を申請することができます。
※「一般」または「現役並み所得者3」の区分に該当される方は被保険者証(保険証)で限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要です(ご自身の区分がわからない場合には、町の後期高齢者医療担当へお問い合わせください)。
令和6年12月2日からは、限度額適用認定証および限度額適用認定・標準負担額減額認定証が新規発行されなくなります。
【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、事前の申請や限度額証がなくても、限度額を超える支払いが免除されるため、マイナ保険証をご利用頂ける場合、限度額証は不要です。
【すでに限度額証をお持ちの方】
お手持ちの限度額証に記載されている有効期限までは利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に記載内容が変更になった場合は、次の「令和6年12月2日以降に新しく限度額証を必要とされる方」と同様の取扱いとなります。
※紛失された場合、有効な保険証をお持ちの場合は再発行が可能です。
【令和6年12月2日以降に新しく限度額証を必要とされる方】
令和6年12月2日以降、新しく限度額証が必要な方には、申請していただくことにより、「資格確認書」に限度額等の区分を記載します。
限度額証の記載内容が変更になった場合は、限度額証が交付できないため、前述のとおり「資格確認書」に限度額等の区分を記載することになります。
※マイナ保険証をご利用の場合でも、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税の方が、入院時の食事代の減額を受ける場合は、事前に大山崎町役場へ届出が必要です。
入院時食事療養費の支給申請(入院時に食事を提供されたとき)
被保険者が入院した場合には、食事にかかる費用のうち以下の表1に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時食事療養費として広域連合が負担します。
低所得者2・1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。
(表1)食事療養費標準負担額
| 所得区分 | 対象 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) | |
| 現役並み所得者3・2・1 | 同一世帯に一人でも住民税課税対象者がいる方。 |
510円 |
|
| 一般 | |||
| 低所得者2 | 同一世帯の全員が住民税非課税の方。 | 過去12か月間の累計 入院日数が90日以内 |
過去12か月間の累計入院日数が90日超※ |
|
240円 |
190円 |
||
| 低所得者1 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方または老齢福祉年金を受給している方。 |
110円 |
|
※直近12ヶ月間の累計入院日数が90日を超える場合の届出について
医療機関で上記の標準負担額が適用されるのは、届出の翌月1日からとなります。
なお、届出日から月末までの食事療養費標準負担額の差額は、申請があれば支給できますので、領収書を持って大山崎町役場までお越しください。
届出日までの差額については、原則支給できません。
入院時生活療養費の支給申請(療養病床に入院したとき)
被保険者が療養病床に入院した場合には、食事と居住にかかる費用のうち以下の表2に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時生活療養費として広域連合が負担します(疾病などにより、さらに負担が軽減される場合もあります)。
低所得者2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。
(表2)生活療養費標準負担額
| 所得区分 | 対象 | 食費標準負担額 (1食あたり) |
居住費標準負担額 (1日あたり) |
|
| 現役並み所得者3・2・1 | 同一世帯に一人でも住民税課税対象者がいる方。 |
510円 |
370円 |
|
| 一般 | ||||
| 低所得者2 | 同一世帯の全員が住民税非課税の方。 | 過去12か月間の累計 入院日数が90日以内 |
過去12か月間の累計入院日数が90日超 | |
|
240円 |
190円 |
|||
| 低所得者1 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
140円 |
||
| 老齢福祉年金を受給している方。 |
110円 |
0円 |
||
申請に必要なもの
- 各種証の交付申請書・届出書(以下からダウンロードすることができます。)
- 来庁者の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
- 過去12か月間の累計入院日数が90日を超える場合は、90日分の入院期間を証明するもの(医療機関の領収書など)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月03日